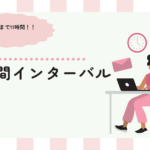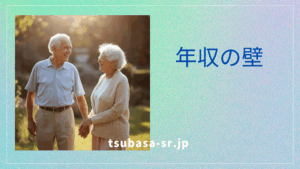働き方改革

働き方改革が目指そうとすることとは?
今日ではみなさんが一度は耳にされたことがあるであろう「働き方改革」ですが、この言葉が国の政策として前面に打ち出されたのは2016年9月のことになります。このブログを執筆している現在から9年前ということになります。安倍内閣の下で発足した「働き方改革実現会議」がスタートになります。翌年の2017年3月には、骨子となる「働き方改革実行計画」を策定、さらに2018年6月には「働き方改革関連法」の成立(8本の法律がまとめて改正されました。)、2019年4月より大企業は全面施行、中小企業は時間外労働の上限規制に対する猶予措置(大企業より1年遅く施行)が採られたうえで施行となりました。(月60時間超の残業の割増賃金引上げ(25%→50%)については、すでに大企業では2010年4月施行の改正労働基準法により適用開始、中小企業は当面の間猶予されていたものが、2023年4月より引上げが義務化されました。)
そもそも、この「働き方改革」が目指したもの、それは働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を実現することでした。そのために、それらの障壁となる長時間労働を是正し、雇用形態(たとえば正社員、契約社員、パートタイマー)によっての不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるようにすることで、多様で柔軟な働き方を働く人それぞれが選択できるようにしようとしました。
まず、長時間労働を是正するための労働時間法制の見直しにより、働き過ぎを防ぎながらワーク・ライフ・バランスの実現を目指しました。代表的なものは、残業時間の上限規制、年5日間の年次有給休暇取得の義務づけ、中小企業における月60 時間超の残業の割増賃金率引上げ(割増率 25%以上→50%以上に)、産業医・ 産業保健機能の強化などが挙げられます。
なお、残業時間の上限規制については大企業は2019年4月から、中小企業は翌2020年4月からの適用とされましたが、さらに2019年4月に改正法施行後、5年間適用猶予を受けていた「自動車運転の業務」「建設事業」「医師」「鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業」についても2024年4月から上限規制が適用されたことで、現在では新技術・新商品等の研究開発業務(医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けることが条件)を除くすべての事業、業務において上限規制が設けられています。
とくに2023年中頃から、トラックドライバーの2024年問題というかたちでメディア等で大きく報じられましたし、医師についても命と向き合う最前線で過酷な労働を余儀なくされ、医師自身に健康被害が生じているという問題についてもずいぶんと取り上げられました。
働き方改革によって、政策効果の実現はいかほどのものかをこれからしっかり検証していく必要があります。たいへん残念なことに現在でも違法な長時間労働があって労働基準監督署からの是正勧告、是正命令あるいは刑事告発といった処分が下される企業が少なくない数いるのも事実です。
また、一方で法令遵守で適切にルールにのっとり残業を削減した結果、労働者目線では、残業を抑制するがゆえに、残業代が減ることで労働者の給与総額が減って今までの生活水準を維持することが困難なケースも発生しています。これまであてにしていた残業代の目減りにより生活が立ち行かなくなると聞けばなんともやるせない気持ちになります。
今後、確実にいえることは、わが国の労働力人口(15歳以上人口のうち就業者と失業者を合わせたもの)は人口減少の流れの中で、これからもしばらくの間減り続けます。最近では「人手不足倒産」なる言葉もよく聞くようになりました。
企業も生き残りをかけた中で人材(人財)の確保は至上命題ともいえます。そうであれば、発想を転換すれば、どうすればおのずと無理なく人材(人財)が確保できるのでしょうか?そこはやはり職場環境の改善に常に前向きに取り組み、魅力ある企業だけがこれから先でも、明るい光が差し込むのではないでしょうか。
そのように捉えますと、働き方改革を1つの契機に魅力ある職場づくりに進んでいただきたいのです。一昔前、企業は「どれだけ儲けたか(稼いだか)!」が重要視されていました。しかし今日では「どのようにして儲けたか!(稼いだか)」が重要であると言われています。時代とともに求められる企業像も変化していきます。
働きがいのある企業にこそ、そこでは新たなアイディアや発想が生まれ、さらなる成長を手にすることができる。経営者のみなさんには、働き方改革を単なる法規制による押しつけとして捉えるのではなくより良い会社にするためのきっかけにしていただきたいと思っています。
この記事を書いた人

-
社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(日本FP 協会認定)
企業とそこで働く従業員双方の立場から、より良い職場環境を構築するための最適解を導き出し、良き伴走者となって積極的に支援します!
最新の投稿
 お知らせ2026年1月5日新年あけましておめでとうございます。
お知らせ2026年1月5日新年あけましておめでとうございます。 ブログ2025年12月24日勤務間インターバル制度
ブログ2025年12月24日勤務間インターバル制度 ブログ2025年11月23日30人の壁??
ブログ2025年11月23日30人の壁?? ブログ2025年11月16日年収の壁
ブログ2025年11月16日年収の壁